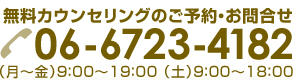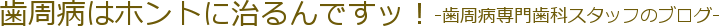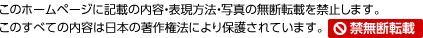口臭
2017年4月1日
カテゴリ:日記
こんにちは。大阪府東大阪市にあります大阪歯周病センタートリートメントコーディネーターの前川です。
今日から新年度です。今年度もしっかり努められるよう気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
今日は口臭についてお話します。
口臭の原因となる要素は、「生理的原因」「病的原因」「外的要因」「内的要因」の4つに分類することができます。
生理的口臭は、起床時や空腹時、過度な緊張状態によるストレス等により、唾液の分泌量が減ることで引き起こされます。
病的原因は歯周病や虫歯、内臓のトラブルによって口臭が発生します。歯周病により歯茎が弱って出血した部分や、歯茎が痩せて歯と歯茎の間が広がった部分に汚れが溜まると、それを細菌が分解することで揮発性ガスが発生し悪臭となります。
外因的要因は臭いの強い食べ物を食べたときや喫煙時に発生しやすくなります。ニンニクにはアリルメチルスルフィドという悪臭の原因成分があり、それが口内、消化器官、肝臓を通って最終的に肺から体外へ排出され、そのにおいは食後約16時間持続するといわれています。タバコを吸うとニコチンが血流の循環を悪くするため、唾液の分泌を減らしてしまいます。また、タールが口内の歯、舌、歯垢に付着することでも口臭が発生しやすくなります。
内因的要因は精神的なストレスや不安感が強い時、検査の結果は異常なくても、本人だけが口臭があると思い込んでしまうことがあります。この状態が続くと、自臭症という病気に発展します。
当院では口臭治療の際、口臭の測定をしたりブラッシングクリーニング等のケアも行っております。気になる方はお声がけください。
大阪歯周病センターへ
ドライソケット
2017年3月25日
カテゴリ:日記
こんにちは。大阪府東大阪市、大阪歯周病センター、歯科衛生士の大下です。
今日は近くの大学の卒業式があり、袴を着た学生さんが歩いておられ、数年前の自分の姿を思い出しました。
さて、皆様は親知らずを含め歯をぬかれたことはございますか?歯を抜いた後医院で、血が止まるまでしっかりガーゼを咬んでいただき、血が止まったことを確認してお帰りいただいておりますが、歯を抜いた後はその時だけでなくご自宅に帰られてからも気をつけておいていただくことがたくさんございます。それはドライソケットという症状がでるかもしれないからなのです。ドライソケットとは、主に下の歯の親知らずを抜いた後に起こり、抜歯した穴が血液で覆われず骨が直接お口の中にむき出しになっている状態のことです。本来、骨は歯茎に覆われていなければいけないのですが、抜歯後何らかの原因で骨の上で血液が固まらなかったため(かさぶたが出来なかったため)、骨の上に歯ぐきが作られず、骨の表面が出たままになっています。食事の際、物が入ると直接骨に触れるために強い痛みを伴います。
•抜歯後2~3日で痛みがでてくる
•ズキズキと激しく痛む
•痛みが長引いて弱まらない(2週間程度、あるいはそれ以上)
•特に飲食時の刺激で痛む
これらが症状です。ドライソケットは親知らずだけではなく、抜歯をした後にはどの歯にも起きる可能性があり、特に下の親知らずを抜いた時に多く起こります。それは下の親知らずの抜歯は難しく、骨を削ることで傷口が大きくなり細菌に感染しやすいことが理由と考えられています。ですから、下の親知らずを抜いた後は特に要注意です。
ドライソケットになる原因は、うがいを何度もしてしまったり、何かを吸う動作をしたり、喫煙をしたり、舌で抜いたところを触ったりと様々ですが、歯を抜いた際には注意事項をお伝えいたしますのでお気を付け下さい。
大阪歯周病センターへ。
噛む効果
2017年3月18日
カテゴリ:日記
こんにちは。大阪歯周病センターの助手の竹原です。最近やっと春らしい暖かい気温になってきました。季節の変わり目には体調管理に気を付けてくださいね。今日は「噛むことの大切さ」についてお話しします。近年、特に子供が“良く噛まない子”“良く噛めない子”“硬い食物を嫌う子”が増えてきています。よく噛まないと、顎の骨の動きや、噛むことに使われている数種の筋肉の発達・発育が遅れます。他にも、歯並びが悪くなったり肥満や、生活習慣病にもなりやすくなります。しっかり噛むことで得られる効果がたくさんあります。一つ目は、唾液の分泌を促しガン予防、歯の病気予防、体力向上につながります。二つ目は、脳を活性化させ、肥満・老化防止になります。三つめは、咬むことにより正常な咬合と歯並びを作ります。そして美しい発音や言葉を生み出します。四つ目は、しっかり噛むことで肥満予防のも繋がります。よく噛むという意識をするだけで生活習慣病を予防出来たり、健康で長生きできるので、皆さんもぜひ今日からたくさん噛むことを意識して、美味しく健康的にお食事を楽しみましょう。目指せ一口30回!!歯周病治療なら大阪歯周病センターへ